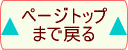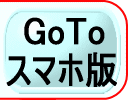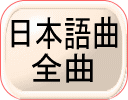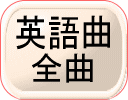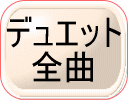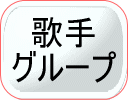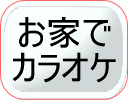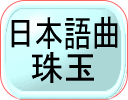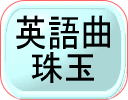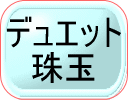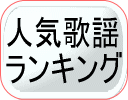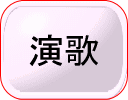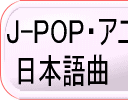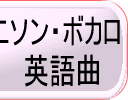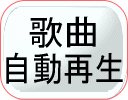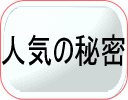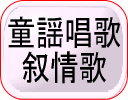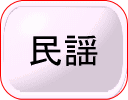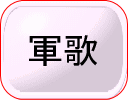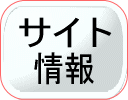|
音程
|
音程とは、二つの音の高さの隔たり(距離)を指す音楽用語です。音程は「ド」と「ミ」や「ソ」と「ド」のように、ある音を基準にしたとき、もう一つの音がどれだけ離れているかという相対的な関係を表します。
音楽では、「音程」を組み合わせることで、メロディーの滑らかさや和音(コード)の明るさ・暗さといった感情的な表現や、音楽的な構造(スケールやコード)を形作っています。
|
|
キー
|
音楽の「キー(Key)」は、日本語では「調(ちょう)」と呼ばれ、その楽曲全体の音の土台、中心、雰囲気を決める非常に重要な概念です。
キーは、主に以下の2つの情報で示されます。
・主音(中心となる音):曲の「ホームポジション」となる音です。メロディーやコードが最終的に落ち着くと感じられる、その曲の中心となる音です。
・調性(曲の雰囲気):その曲がどんな音階の構造を持っているかを示し、曲の全体的な雰囲気を決定づけます。
|
十八番
(おはこ)
|
自分の一番得意な曲のこと。ここぞという時に歌う、自信のある持ち歌です。
音楽での「十八番」とは、その人が最も得意とする曲や、自信を持って披露できる演奏(レパートリー)のことを意味します。
カラオケでで「あなたの十八番は何?」と聞かれたら、「あなたの持ち歌や得意な歌は何ですか?」という意味になります。
|
|
アニソン
|
「アニメソング」の略称。アニメの主題歌・挿入歌はもちろん、アニメに 使われていなくても、アニメ声優が歌う曲も含まれる場合が多い。
|
|
ゲーソン
|
「ゲームソング」の略称。ゲームに使われた歌詞入りの曲。
|
|
ボカロ
|
「ボカロ」とは、ヤマハが開発した歌声合成技術である「ボーカロイド」(VOCALOID)の略号として使われる言葉ですが、それを用いた応用製品の総称をも含みます。
〔ボカロの特徴〕
・メロディーと歌詞を入力するだけで、人間の声を元にした歌声を合成します。
・人間の歌声データ「歌声ライブラリ」と、歌唱編集ソフト「VOCALOIDエディター」とを組み合わせて使用されます。
・ボーカロイドにより作られた楽曲は「ボカロ曲」と呼ばれ、制作者は「ボカロP」(ボカロプロデューサー)と呼ばれます。
・「初音ミク」や「鏡音リン・レン」など独自のキャラクターデザインと声の特徴を持つボーカロイドなどがあります。
|
|
デュエット
|
音楽の分野における「デュエット」(Duet)は、主に「二重唱」や「二重奏」を意味する言葉です。
・二重唱(歌): 2人の歌手が一緒に歌うこと、またはその楽曲。特にポピュラーソングなどでは、男女ボーカルが歌う曲を指すことが多いです。同性同士の場合は「デュオ」とも呼ばれます。
・二重奏(演奏): 2つの楽器で演奏すること、またはその楽曲。
|
|
ハモる
|
伴奏に合わせて、主旋律とは異なる音程で歌うこと。
「ハモる」は、音楽用語の「ハーモニー」(harmony)を略して動詞化した言葉です。
歌唱においては、主旋律(メインメロディー)に対して、別の人がそれと協和する違う音程のメロディー(ハモリ・コーラス・副旋律)を付けて歌うことを指します。
これにより、曲に深みや厚みが生まれます。
単に皆んなで同じメロディーを歌う場合は「斉唱(ユニゾン)」となります。
|
ユニゾン
(斉唱)
|
「ユニゾン (Unison)」は、「一つの音」という意味の英語(unison)に由来する言葉です。
ユニゾンとは、複数の歌手や演奏者が、リズムも音程も全く同じ旋律を同時に歌ったり演奏したりする演奏形態をいいます。
厳密に同じ音程でなくても、男性と女性がオクターブ違いで同じメロディーを歌う場合などもユニゾンと見なされます。
|
|
エコー
|
エコーとは、日本語の「反響」や「こだま」を意味します。音源から出た音が、遠くの壁や山などに反射して、元の音と区別できるほど遅れてはっきり聞こえ直す現象です。
繰り返される音が明確に聞こえるため、山びこのように「ヤッホー、ヤッホー...」と聞こえるような効果を生み出します。適度なエコーなら、歌声に残響効果がかかり臨場感あるカラオケを楽しむことができます。
|
|
リバーブ
|
「リバーブ」は日本語で「残響」と呼ばれます。
音源から出た音が、壁や床・天井など周囲の様々な表面に短時間で何回も反射し、その反射音が複雑に重なり合うことで、元の音が途切れた後も「音の尾」として響き続ける現象です。
教会やホールなどの広い空間の臨場感や空間の広がりを音に与えるために使われます。
|
|
ハウリング
|
マイクがスピーカーの音を拾い、「キーン」という不快な音が発生する現象のことで「ハウる」などとも言う。
こんな状態を続けているとスピーカーのコイルが撥ねて吹き飛んでしまうことがありとても危険です。
|